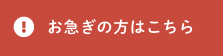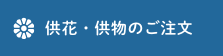【宗派ごとに異なるお線香の本数と供え方】
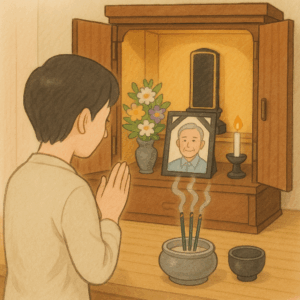
~五島地域の慣習とあわせて~
お盆のお墓参りや法要の際に、「お線香は何本立てればいいの?」と迷う方は少なくありません。
実は、お線香の供え方には宗派や地域ごとの違いがあり、明確な“正解”があるわけではありません。
今回は、代表的な宗派の供え方の違いに加えて、五島地域に根づく慣習もご紹介します。
🔸 浄土真宗(本願寺派・大谷派など)
-
お線香は折って、火をつけたあと香炉に横に寝かせる
-
本数は 1本でOK、立てないのが正式な作法
▶ 供養の意味
浄土真宗では、**「香りを仏さまにお供えする」**という考え方が基本です。
線香を燃やして煙を立てるのではなく、香りそのものを仏前に捧げる=敬意と感謝のしるしとされています。
修行や煩悩を焼き尽くすためのものではなく、信仰のあらわれとして香をそなえる行為とされています。
🔸 浄土宗
-
基本は 1本または2本を立てて供える
-
お墓参りでは3本立てる方も多い
▶ 供養の意味
浄土宗では、線香は煩悩を焼き清め、清浄な心で仏に向き合うためのものとされています。
1本は仏さまへの供養、2本は仏と故人への供養、3本は三宝(仏・法・僧)を表すという解釈もあります。
🔸 曹洞宗(禅宗)
-
1本立てるのが基本
-
法要など複数人で供える場面では3本になることも
▶ 意味
シンプルに仏さまへ向き合う心を大切にし、「形にとらわれすぎず、丁寧に手を合わせること」が重視されます。
🔸 臨済宗(禅宗)
-
基本は 1本立てる
-
状況によって3本立てることもあります
▶ 特徴
臨済宗も曹洞宗同様、「心を整える香」として線香を使います。修行の一環という意識が強いです。
🔸 日蓮宗
-
一般的には 3本立てる
-
三宝(仏・法・僧)への敬意を表す意味があります
🔸 真言宗
-
正式には 3本立てる
-
三密(身・口・意)や三世(過去・現在・未来)を意味します
🔸 天台宗
-
1本または3本を立てる
-
地域や家庭の習慣により差がありますが、いずれも丁寧に供える心が重視されます
【五島での一般的な慣習】
五島地域では、宗派に関わらず以下のような線香の供え方をされる方が多く見られます:
-
亡くなられてから葬儀までの間(枕経・通夜・葬儀):
→ 線香は1本立てる -
葬儀が終わったあとの供養(初七日・四十九日・お盆・法事など):
→ 線香は2本立てる
この背景には、故人が旅立つまでの間は「静かに寄り添う気持ち」、葬儀後は「仏・故人の霊」など二者への供養という意味合いがあるとも言われています。